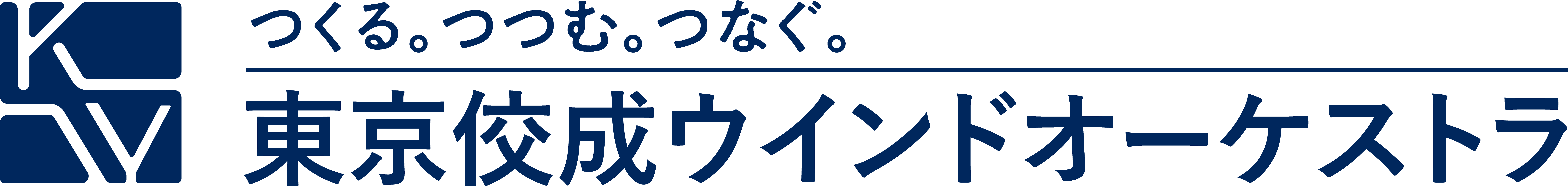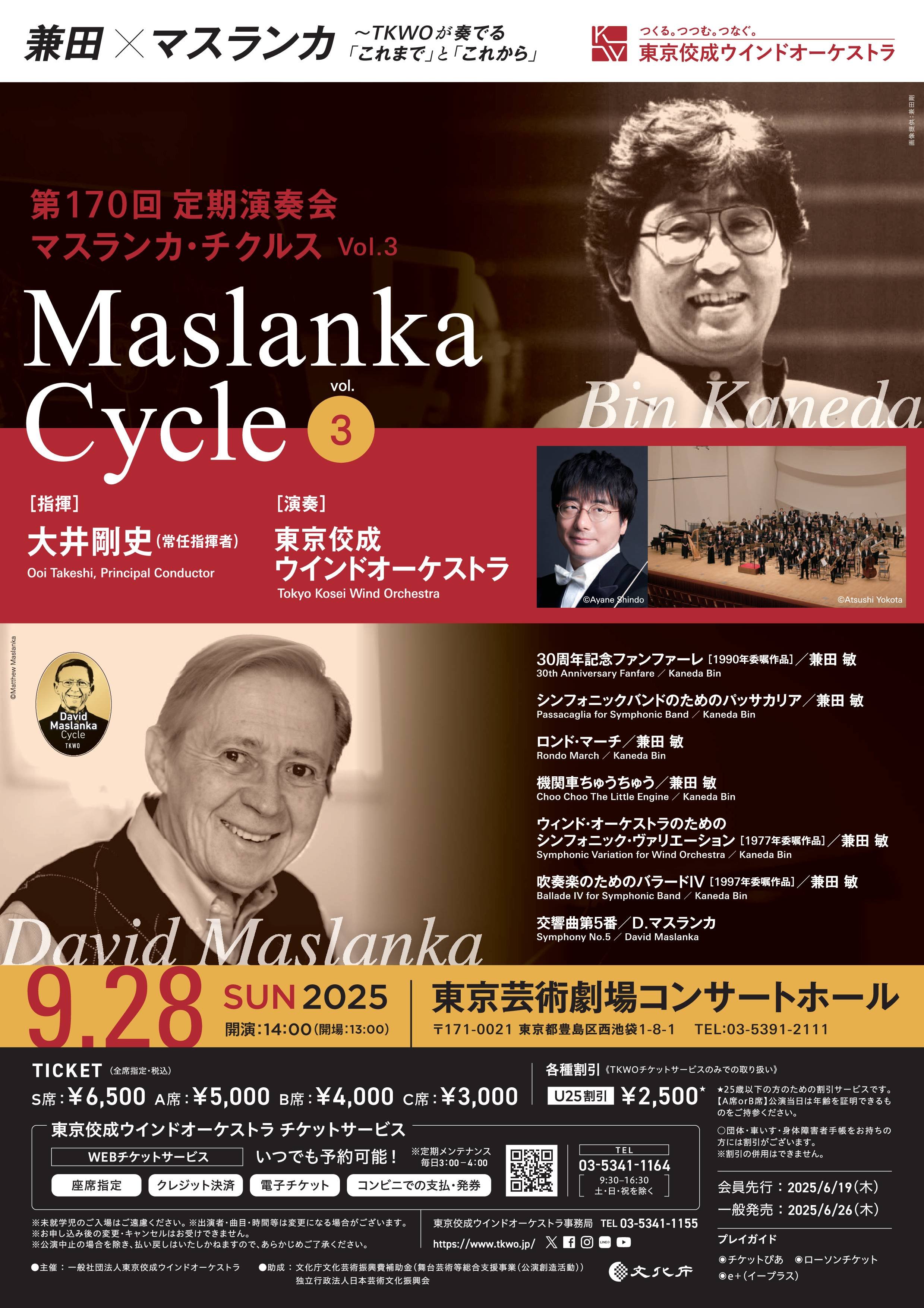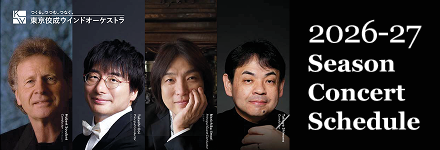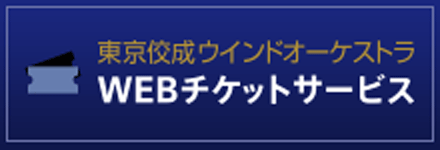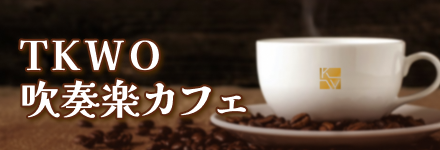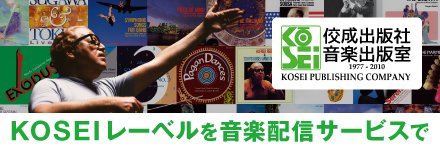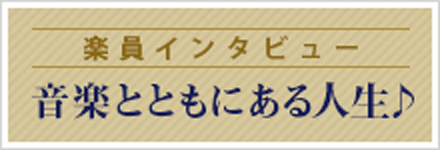9月28日に開催される東京佼成ウインドオーケストラ第170回定期演奏会では、前半に日本吹奏楽界のレジェンド、兼田敏(1935-2002)の生誕90年を記念した特集プログラムをお送りします。日本吹奏楽界に多大な功績を残した兼田敏とは、一体どのような人物だったのでしょうか。兼田敏の愛弟子である作曲家・成本理香さんと、東京佼成ウインドオーケストラ楽芸員の中橋愛生が、兼田敏の知られざる素顔に迫ります。
成本理香
和歌山市生まれ。中学時代は吹奏楽部で打楽器を、高校時代はフルートを担当。愛知県立芸術大学音楽学部作曲専攻を首席で卒業、桑原賞受賞。同大学院修士課程、博士後期課程修了。同大学初の作曲分野での博士号を取得。入野賞(1位)、Iron
Composer
Competition第3位(アメリカ)、愛知県芸術文化選奨新人賞など多数の受賞歴がある。Asian
Cultural
Council(アメリカ)フェローに選出され招聘を受けてニューヨークに居住してアメリカの現代芸術研究に従事、帰国直前に行った自作自演を含む個展(リサイタル)は好評を博した。現在は名古屋と金沢を拠点に「クロス・ジャンル(ジャンルの越境)」を主なテーマとして創作活動を行なっており、その作品は世界各国のフェスティバルやコンサートで演奏されている。現在、愛知県立芸術大学教授、2024年度から音楽学部長兼大学院研究科長を務める。金城学院大学、名古屋芸術大学講師。
兼田敏ってどんな人?
思い出の「食堂兼田」
なぜバラード?
『バラードIV』と晩年の兼田
本当に伝えたかったこと
吹奏楽のすすめ
謎の小品「ロンド・マーチ」「機関車ちゅうちゅう」
師匠と弟子の関係
音楽を愛した「音楽家・兼田敏」
今回の対談からは、兼田敏の飾らない人柄と、音楽に対する真摯な姿勢が浮かび上がってきました。9月28日の東京佼成ウインドオーケストラ第170回定期演奏会では、そんな兼田敏の多様な作品を通して、彼の音楽の奥深さと魅力に触れることができるでしょう。ぜひ会場に足をお運びください。