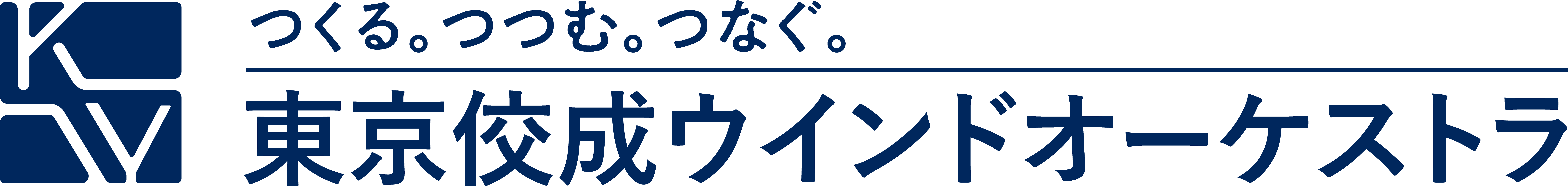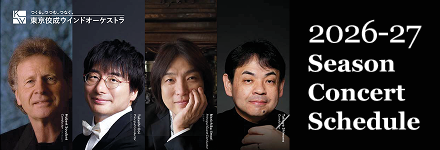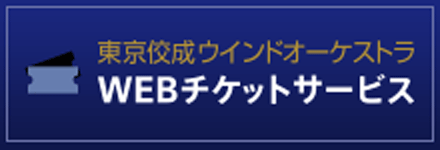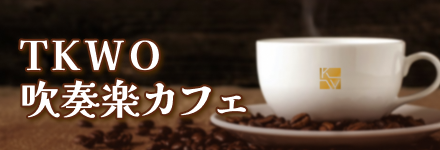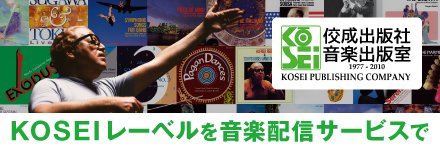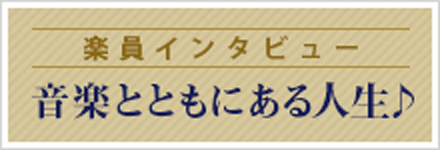こんにちは♪私は今、吹奏楽でフルートを吹いています。
コンクール前に、
「音が混ざらないから自分だけ浮いて聞こえるときがない?」
「繊細さが足らない」
と、言われました。
でも、私自身の吹いている音が浮いているようには感じていました。
ですが「混ざりやすい音」や「繊細な音」というのがよくわかりません。
どうしたら混ざりやすい繊細な音になりますか?
また、私の吹くフルートの音はかなり冷たくて硬い音がしている気がします。
暖かくて丸みのある柔らかい音を目指すにはどうすればよいですか?
質問が多くなってしまってすみません。
よろしくおねがいします。
こんにちは♪
まずご質問者様に一つお伝えしておきたいことがあります。
それは、音色というのは聴く人によって持つイメージが違うものなので、
『私はこういう音色だと思っている』と思っても、周りの人が全員そう感じているか
というと、そうではないということです。
これが音楽(芸術)の面白く、また難しい部分なのですが、何が言いたいかというと、
全ての判断を周りの人の感想・意見に任せないで大丈夫です、ということです。
ただそうは言っても、合奏体の中で吹いている以上周囲の楽器と上手に
コンタクトしていかないといけないので、まずは"こういう風に吹くと、大抵の人が
こんなイメージを持つ"というデータを頭の中に入れることが必要でしょう。
・「音が混ざらないから自分だけ浮いて聞こえるときがない?」
・「繊細さが足らない」
という上記の情報を元に解析すると、恐らくですがご質問者様の奏法というのは、
比較的管体を外側に傾けて吹いていませんか?
重ねると、唄口も下唇でほぼ塞いでいない状態ではないでしょうか?
物理的に言いいますと、「外側に傾く=唄口が開く=唇から射出された息が
リッププレートのエッジに到達するまでの距離が長くなる」という現象になります。
これは一般論からすると、拡散していく無駄になる息が増えることを表すので、
音色は実際のところシャーリングが増し、人が聴いた感覚として音色が荒れた
(ガサガサになった)と感じることが多いでしょう。
これを改善するためには、唄口を約半分くらい下唇で塞ぎ、上唇も少しかぶせ気味
の位置関係にして、アンブシュアも可能な限り息がまとまるようなアンブシュアを
作られるようにしてみてください。
この時に、まとめすぎて音色が暗くなったり、こもったりしていないか注意してください。
これで以前よりはシャーリングも減るので、音色は柔らかく感じるはずです。
「丸みのある・・・・」という表現もありましたが、もしかしたらタンギングの強さも
影響している可能性があります。
タンギングのアタックがキツいと、音色もキツい・固いという印象を持たれがちです。
上記のようなところを改善のポイントとして、音色創りをされてみてくださいね。
頑張ってください♪
【Fl.&Picc.丸田悠太♪】