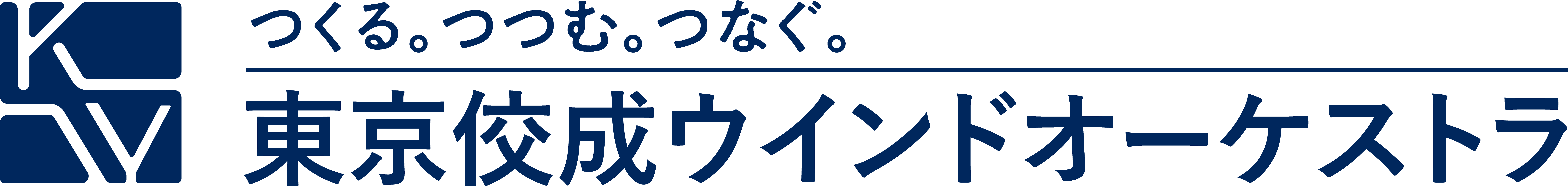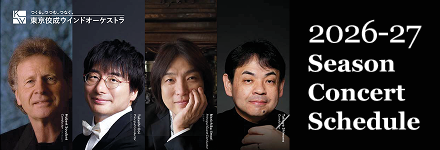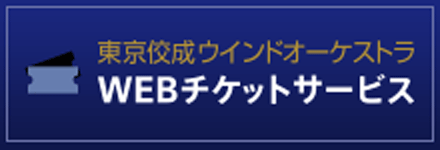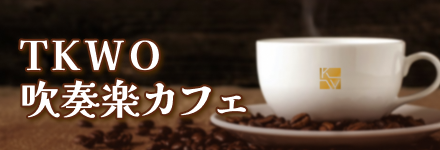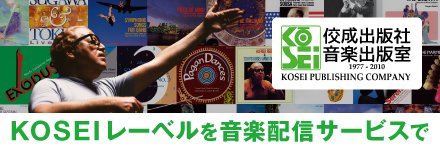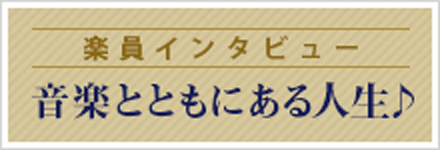とある本で、ドイツ奏法とフランス奏法というのが出てきました。その本には、今ではほとんど議論されることは無くなった、とありましたが、ドイツ奏法・フランス奏法とはどんなものですか?
フルートの奏法についてのご質問ですが、この奏法の違いというのを文章だけでご説明するのはなかなか難しいのですが、あくまで参考程度としてお考えください♪
正直申し上げて、現代のフルート界においてはドイツとフランスの奏法(考え方)の違いは、昔ほど無くなっていると思います。
まず奏法というより、ドイツとフランスにおいて"フルート"という楽器に対しての"音の理想像"が違っていたことに端を発します。
ドイツでは
「トランペットが鳴り響くような音」
というような、豊かな響きと力強さをイメージとして持っていたようで、対してフランスでは
「ソフトで優しい音」
といった、大変柔らかく繊細なイメージでしょうか。
やはり、ドイツで言えばベートーヴェンやブラームス、ワーグナーだったり、
フランスで言えばドビュッシーやラヴェルといった様に、それぞれの国を代表する作曲家の作品などを考えると、音の傾向に差が生じるのも納得がいくような気がします。
更に、金属管フルートが発明されて以降ですが、
ドイツでは「管厚が厚く、カバードキィ」、フランスでは「管厚が薄く、リングキィ」
という様に、好んで使われた楽器にも違いがあります。
これも要因の一つと考えられるでしょう。
そして、一番重要な"奏法の違い"についてですが、
ドイツでは、息を唄口(アンブシュアホール)に対して斜め45°よりも浅く、比較的太い息で、いわゆる"外吹き"という様な吹き方。アンブシュアは、しっかりと筒を造る様な形。音量は大きくなるが、シャーリングも大きくなる。太く、力強い音色。
フランスでは、唄口に対して垂直に近い角度で吹き下ろし、比較的細い息で、アンブシュアも唇を横に引く様な形。音量はそんなに大きくないが、シャーリングも少ない。丸く、柔らかい音色。
ざっくりとしたイメージと資料からの情報ですが、上記のような感じだと思います。
この、ドイツとフランスの奏法の違いについて述べている文献があまり少ないため、なかなか分かりにくい点が多いと思います。
僕個人的なイメージとしては、様々な物の造り(車や生活用品等の色々な物)や、歴史的な流れを含めて考えると、この奏法の違いは"国民性の違い"から来ている、当然の結果のような気がします
(´ー`)
面白いものですね♪
始めにも書きましたが、あくまでも参考としてお考えくださいm(_ _)m
【Picc.丸田 悠太♪】