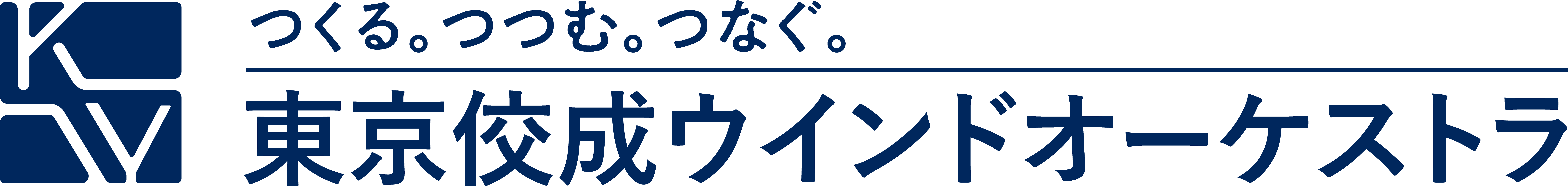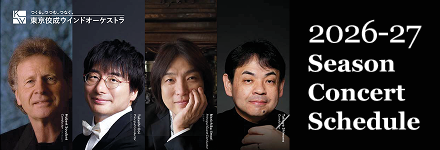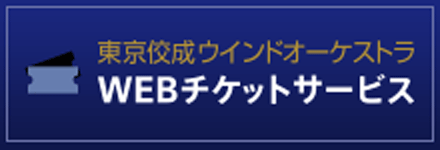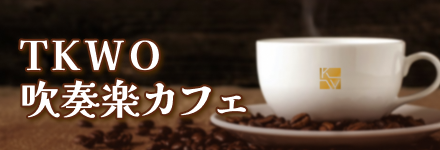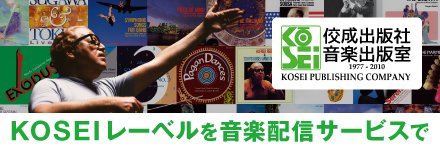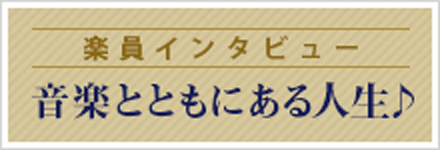吹奏楽のなかで、
「客席に届くような音を出す」にはどうしたらいいでしょうか。うまくコツがつかめません。
合奏の録音を聴いても、聞こえてほしいフレーズが埋もれてしまったりします。(2nd、3rdの重要なフレーズなど。)
「もっと鳴らして」と言われるので、自分では頑張って息を入れているつもりなのですが、音が立ちません。
きつい汚い音にしてまで鳴らすのも嫌だな・・・と内心思ってしまったり。
昔ある方に「ステージ上ではきつくて荒っぽく聞こえるぐらいの方が、客席ではちょうど良く聞こえる」なんて言われたこともあるのですが、実際はどうなんでしょうか?
プロの方々の音はすぐそばで聞いても丸くて良い音と感じるものだと思っているのですが・・・。
日本人が陥りやすく、またとても大切な質問ですね!
私が思うには「遠鳴りする音」とは「豊かな倍音を含んだ音」です。
倍音を含んだ・・・とは、言葉で説明するのは難しいのですが、
分かり易く言えば、ちゃんとリードの響きをさせた音・・・とでも言えましょうか?
これは私が留学経験などで気付いたことですが、
どうやら西洋人は元々こういう音を感覚として持っているようです。
ところが日本人は、もっと響きの暗い「こもった音」が好きで、
ちゃんと響きのある倍音の豊かな音を「汚ない」と感じる人が多いようです。
そして、倍音をそぎ落としてしまったエレクトーンのような音を
「丸い音」「太い音」と好む傾向があるようです。
プロの世界にもそういう人はたくさんいます。
そういう人達は、そばで聴くと耳当たりの良い音がしますが、
やはり遠鳴りしない場合が多いようです。
逆に隣で聴いていると開いたキツい音のように思えても
客席で聴くと美しく響いている・・・ということもあります。
自分の音を客席で客観的に聴けないので判断は難しいですが、
単純に言うと「効率良く鳴っている音」が大切です。
響きを抑えてそれを「丸く温かい音」と勘違いしないように
くれぐれも注意してください。
大浦綾子